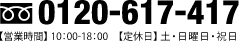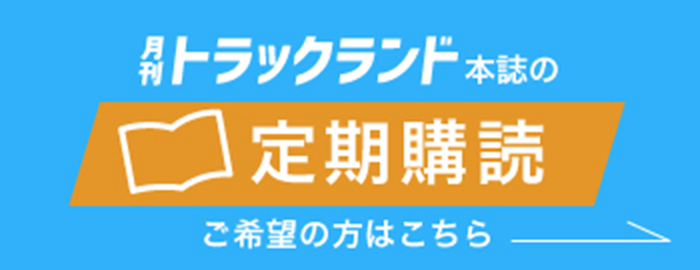「準中型免許の取得を検討している」「準中型免許で乗れるトラックについて知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、免許制度の概要をはじめ、準中型免許で乗れるトラックの種類、免許の取得方法などを解説します。
準中型免許で乗れるトラックを多数扱うトラックランドについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
準中型免許とは?
2017年3月12日に新設された運転免許制度で、普通免許と中型免許の間に位置します。準中型免許は、自動車による交通死亡事故の削減や若年層の雇用促進を目的に導入されました。
この免許制度の導入により、18歳からより幅広い車両を運転できるようになり、運送業界や物流業界での人材確保や若年層の運転機会の増加に寄与しています。
普通免許では運転できない、やや大きめのトラックも準中型免許を取得することで運転できるようになります。
準中型免許で乗れるトラック

車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満のトラックが準中型免許で乗れるトラックです。
具体的には、配送業や引越業、建設現場で使用されるトラックが含まれ、例えば、三菱ふそうの「キャンター」やいすゞの「エルフ」、日野自動車の「デュトロ」などが代表的なモデルです。
【いすゞ自動車(エルフ)】
高い積載能力と燃費性能が特徴のトラックで、ブリクラッシュブレーキや、車間距離警報、車線逸脱警報(LDWS)などの安全性能も充実しています。
【三菱ふそう(キャンター)】
同じく積載量が多く、燃費性能も良いトラックで、衝突被害軽減ブレーキ機能を搭載しており、安全性の高さもあります。世界初の完全電気駆動小型トラック「e-Canter」も展開しています。
【日野自動車(デュトロ)】
1999年に日野レンジャー2/3の後継モデルとして登場したトラックで、トヨタ自動車との共同開発により、高い品質、コストパフォーマンスを実現しています。
これらのトラックは、重量物や大量の荷物を効率よく運搬するために設計されており、さまざまな業種で活躍しています。
中型免許との違い
中型免許は、2007年に普通免許と大型免許の間として新設された運転免許制度で、車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量が4.5トン以上6.5トン未満のトラックを運転することができます。
取得条件は、準中型免許とは異なり、基本的に普通免許や準中型免許を取得してから通算2年以上の運転経験が必要です。そのため、年齢も20歳以上でなければ取得できません。一方で、準中型免許は18歳から取得可能です。
準中型5t限定免許との違い
準中型5t限定免許とは、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方に対して、自動的に適用された免許のことです。
この免許により、車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トン未満のトラックを運転することができます。2017年3月12日以降、普通免許の制度が変更され、準中型免許が新設されたため、この期間に普通免許を取得した方は、自動的に「準中型5トン限定免許」として扱われることになりました。
この免許は特定の期間に取得した方にのみ適用され、普通免許を取得した時期によって運転可能な車両が異なる点に注意が必要です。
準中型免許の取得方法

準中型免許の取得条件や取得方法を紹介します。
取得条件
まず、準中型免許を取得するためには満18歳以上であることが基本的な要件です。視力に関しては、両眼で0.8以上、片眼で0.5以上の視力が必要とされ、これに加えて深視力検査で誤差が2センチ以内であることが求められます。
聴力については、10メートル離れた場所で90デシベルの音を聞き取ることができることが条件となりますが、補聴器を使用している場合も認められます。
取得方法
免許を取得する方法としては、自動車学校に通って教習を受ける方法と、運転免許試験場で一発試験を受ける方法の2つがあります。ただし、自動車学校に通う方法が一般的です。
自動車学校での取得は、視力検査や適性検査を通過したのち、学科と技能の教習を受けます。技能教習では、トラックの運転操作や道路交通法を学び、試験に合格することで免許が取得できます。自動車学校では、運転技術の向上を目的とした実践的な教習が行われ、合宿や通学のスタイルで選べるため、効率的に免許を取得できます。
一方、一発試験は、自動車学校に通わずに、運転免許試験場で直接試験を受けて免許を取得する方法です。一発試験では、学科試験と技能試験の両方に合格する必要がありますが、試験内容は非常に難しく、合格率も低いです。特に、トラックの運転経験が少ない人や、しっかりとした技術を身につけたい方は、自動車学校に通う方法が推奨されます。
取得費用
取得費用は、普通免許を持っているかどうかによって異なります。普通免許を持っている場合、取得費用はおおよそ15万~20万円程度です。一方、普通免許を持っていない場合は、30万~40万円程度かかります。
この費用には、教習所での学科教習や技能教習、教習に必要な教材費や試験料などが含まれます。各教習所によって費用は多少異なるため、事前に確認することが重要です。
準中型免許で乗れるトラックをお探しなら

準中型免許で乗れるトラックをお探しであれば、ぜひトラックランドをご利用ください。トラックランドは全国にネットワークがあり、豊富な種類の中古トラックを取り扱う専門店です。
お客様のニーズに合わせて最適な車両をご提供できるよう、常に在庫を豊富に取り揃え、準中型免許で乗れるトラックも多く扱っています。ご希望の車両が在庫にない場合でも、車両探しをサポートするサービスもございます。
中古トラックを安心してご購入いただくために、徹底した品質管理を行っているのも特徴の一つです。仕入れの段階から整備士が詳細な検査を実施し、車両センターに入庫した後も徹底的な整備・点検を行っています。
架装や車検、板金塗装、陸送サービスまで一貫してサポートしており、安心してご利用いただける万全の体制を整えています。
さらに、定額料金でトラックを活用できるサブスクリプションサービス「サブスク deスグのり」も提供しており、初期費用を抑えながら定額でトラックを利用することができます。必要な期間に応じて柔軟な選択が可能ですので、リースやレンタルをお考えの方には最適です。
準中型免許で乗れるトラックの購入・リースをお考えの際には、ぜひトラックランドにご相談ください。
準中型免許で乗れるトラックについて
この記事では、準中型免許で乗れるトラックの種類や、中型免許、準中型5t限定免許との違い、そして免許の取得方法などについて解説しました。
準中型免許は、交通安全の強化や物流・運送業界での若年者の雇用促進を目的に新設された免許です。準中型免許があれば、車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量が2トン以上4.5トン未満のトラックを運転できます。
免許を取得することで、物流・運送業界でのキャリアを広げる第一歩を踏み出すことができますので、取得を検討している場合にはぜひ参考にしてください。
なお、トラックランドでは、準中型免許で乗れるトラックも幅広く取り揃えています。厳格な品質管理を徹底し、購入後のアフターサポートも充実しておりますので、準中型免許で乗れるトラックをお探しの際は、ぜひご相談ください。
この記事を監修した人
 トラックランド管理人:高良
トラックランド管理人:高良
神奈川県出身。株式会社タカネットサービスの9年目の社員。
これまでに監修した記事は200件以上!中古トラックに関する豊富な知識と経験を活かし、中古トラック業界の最新情報やお役立ち情報を発信しています。
実際のトラック販売やメンテナンスにも精通しており、読者にとって有益な情報をわかりやすく提供することを心がけています。
趣味は野球観戦で、休日には球場でリフレッシュするのが楽しみの一つ。
「月刊トラックランドオンライン」にて、中古トラック選びのコツや業界の最新情報を発信中。
ぜひチェックしてください!