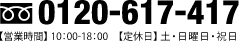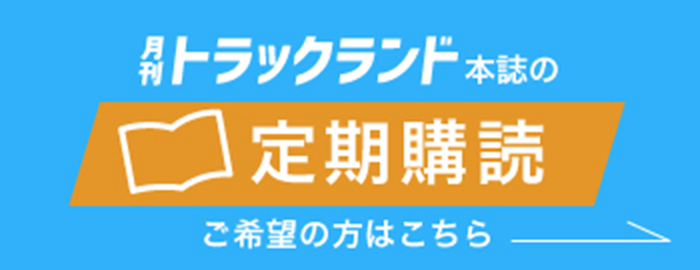トラックに限らず、煽り運転がニュースやSNSで話題になることが増えている昨今。社会的な注目度の高さから、企業をはじめドライバー一人ひとりが危機意識を持ち、対策をすることが求められます。
今回の記事では、トラックによる煽り運転が起きる背景や具体的なトラブルの原因、ドライバーが知っておくべき対策や心構えなどを解説していきます。
煽り運転の加害者、被害者にならないためにもぜひチェックしてください。
煽り運転とは?
他の車両に対して不必要に接近、急な割り込み、蛇行運転、幅寄せ、急ブレーキなどの威圧的な運転行為を繰り返すことで、相手に恐怖や危険を感じさせる行為を指します。道路交通法では「妨害運転」として規定されており、重大な交通違反となります。
特にトラックなど大型車両による煽り運転は、車体の大きさや重量から危険性が高く、一般車に大きな心理的圧力を与えることもあります。そうした行為は感情的なトラブルに発展するだけでなく、事故の発生や社会的批判にもつながります。
トラックによる煽り運転が発生する原因は?

多くのトラックドライバーが安全運転を心がけている一方で、ごく一部で煽り運転が発生しているのは事実です。その背景には、職業運転ならではの環境や心理的な要因が存在します。
ここでは、トラックによる煽り運転が発生する主な原因を解説します。
時間に追われた運行スケジュール
配送業務では、決められた時間内に複数の荷主や納品先を回ることが求められるため、少しの遅延も大きな問題となります。そのため、渋滞などによる時間の遅れを取り戻そうと、無意識にスピードを上げたり、前走車に対して強引に進路を譲らせようとしたりするドライバーがいます。特に繁忙期や深夜帯では、予定通りに走れないことが焦りや苛立ちにつながり、煽り運転と見なされるような行為に発展することがあるのです。
運転中のストレス・疲労の蓄積
長時間運転による疲労や、荷待ち時間の長さ、運送先での対応など、トラックドライバーには常に多くのストレスがかかっています。そうした環境のなかでは、些細な交通状況にも敏感になりがちで、気持ちに余裕がなくなることもあります。
精神的に追い詰められた状態では、冷静な判断や適切な車間距離の保持が難しくなり、感情的な運転へと変わってしまう可能性があります。慢性的な疲労は危険運転の引き金になりやすいのです。
他車のマナー違反への反応
突然の車線変更や合流時の強引な割り込み、信号無視など、周囲の一般車によるマナー違反がトラブルの火種になることもあります。「自分は悪くない」と感じたドライバーが、報復的な行動として車間を詰めたりクラクションを鳴らすなどしてしまうケースも見られます。
大型車は視界が限られているため、前方車両の行動に対して過敏になりやすく、些細なことがきっかけとなり冷静さを欠いた煽り運転につながることがあります。
車両サイズによる誤解や優越感
トラックはその大きさと重さから、一般車に比べて存在感があります。そのため、車両の大きさを力と捉えてしまい、他車に対して優位に振る舞おうとする心理が働くことがあります。
「道を譲ってもらって当然」「遅い車は邪魔」といった誤った思い込みが、車間を詰める、プレッシャーをかけるなどの行為につながるのです。また、経験年数の長さや職業ドライバーとしての自負が過剰な自信に変わると、傲慢な運転を招きかねません。
企業が取るべき煽り運転対策

煽り運転による社会的批判や信用低下を防ぐためには、運送会社や企業全体での対策が不可欠です。個人のドライバーによる感情的運転であっても、会社名が入った車両であれば企業の信頼に直結する問題になります。そのため、企業として煽り運転を「起こさせない」「起きたときに早期発見する」ための体制づくりが求められます。
まず重要なのは教育の徹底です。安全運転講習やヒヤリハット事例の共有、安全運転の継続的な啓発により、煽り運転の発生を予防します。単に法律を伝えるだけでなく、煽り運転が起こる心理的な背景や、自身の行動が相手にどう映るかを具体的に伝えると効果的です。
運行スケジュールの見直しも有効です。タイトな納品時間や無理のあるルートは、ドライバーに精神的負担をかけ、トラブルが起きやすい状況になります。ゆとりある運行計画を立て、急かされない環境を整えることが、煽り運転の未然防止につながります。
さらに、車両へのドライブレコーダーや運転診断システムの導入も効果的です。万一のトラブル時の記録として活用できるだけでなく、運転傾向の可視化により、注意すべき行動を早期に把握できます。
企業全体で煽り運転を「許さない文化」を根付かせることで、ドライバーの意識変化と安全な輸送体制の構築につながります。
トラックドライバーが心がけるべきこと

煽り運転は一瞬の感情や不注意が引き金となり、重大な事故や社会的批判につながるリスクがあります。加害者にも被害者にもならないために、トラックドライバー一人ひとりが常に冷静かつ安全運転を心がけることが重要です。
基本となるのは十分な車間距離の確保です。トラックは制動距離が長く、接近しすぎるとそれだけで威圧的に感じられる場合があります。たとえ前の車が遅く感じても、無理な追い越しや急接近は控え、流れに合わせた走行を心がけましょう。
また、感情に流されない冷静な判断も不可欠です。渋滞や他車のマナー違反に直面した際でも、「自分は職業ドライバーである」という意識を持ち、感情的な行動は慎むようにします。万が一、不快な場面に遭遇した場合は、深呼吸をするなどして一度気持ちを落ち着かせることが大切です。
自車が周囲からどう見られているかを意識することも重要です。大型車は存在感が強く、何気ない動きでも「煽られている」と受け取られることがあります。ウインカーを早めに出す、急な車線変更を避けるなど、周囲のドライバーが安心して行動できるような運転を意識しましょう。
日常的な体調管理と休憩の確保も安全運転に直結します。疲労や眠気が冷静さや判断力を鈍らせることがあるため、無理な運行は避け、しっかりとした休憩時間を取ることが煽り運転防止にもつながります。
煽り運転の加害者・被害者にならないために
トラックによる煽り運転は、ドライバーの心理的要因や運行環境に起因するケースが多く、事故発生や企業イメージの低下につながる重大な問題です。加害者にも被害者にもならないためには、ドライバー自身が冷静な運転を心がけることが不可欠です。
車間距離の保持や感情に流されない運転を心がけることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
なお、トラックの購入や買い替えの際にはぜひ「トラックランド」にご相談ください。高品質な中古トラックを適正価格でご提供しており、ご希望の車両が在庫にない場合でも、全国のネットワークを活用して最適な1台をお探ししております。
買取、販売、リース(サブスク)、陸送、メンテナンスのワンストップ対応が可能ですので、ご興味がございましたらぜひ詳細をご覧ください。
この記事を監修した人
 トラックランド管理人:高良
トラックランド管理人:高良
神奈川県出身。株式会社タカネットサービスの9年目の社員。
これまでに監修した記事は200件以上!中古トラックに関する豊富な知識と経験を活かし、中古トラック業界の最新情報やお役立ち情報を発信しています。
実際のトラック販売やメンテナンスにも精通しており、読者にとって有益な情報をわかりやすく提供することを心がけています。
趣味は野球観戦で、休日には球場でリフレッシュするのが楽しみの一つ。
「月刊トラックランドオンライン」にて、中古トラック選びのコツや業界の最新情報を発信中。
ぜひチェックしてください!