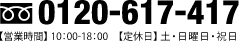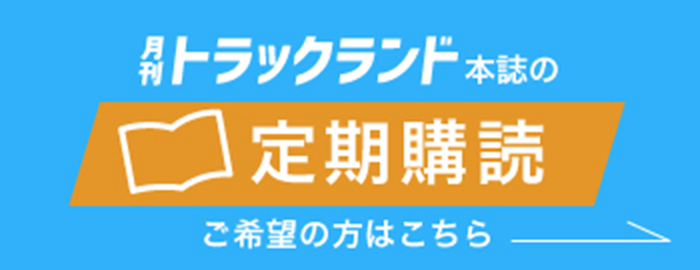「食欲に任せてつい食べ過ぎてしまった経験」は誰しも一度はあるのではないでしょうか。美味しい食事や特別な席では、つい普段以上に口にしてしまいがちです。
ただ、食べ過ぎは体調不良の原因になることがありますので注意が必要です。さらに繰り返すことで、生活習慣病のリスクを高めることにもつながりかねません。
この記事では、食べ過ぎによって起こる主な症状や体への影響、そして日常生活の中でできる予防法などを解説します。
食べ過ぎによって起こる主な症状
食べ過ぎによって起こる主な症状として「胃もたれ」「胸やけ」「胃痛」「吐き気・嘔吐」「腹痛」などが挙げられます。
胃もたれ
食べ過ぎによって胃の中に食べ物が大量に溜まると、消化が追いつかず、重苦しい不快感や消化不良を感じる「胃もたれ」が起こります。特に脂っこい食べ物や甘いものは消化に時間がかかり、胃もたれが起こりやすいです。
胸やけ
食べ過ぎると胃酸が過剰に分泌され、胃の中にあるものが逆流することで「胸やけ」が起こります。胸の奥が焼けるように感じたり、酸っぱい液体が喉元まで上がってくることもあります。
胃痛
胃が過度に膨らむことで胃粘膜に負担がかかり、収縮や炎症を伴って「胃痛」が生じることもあります。
吐き気・嘔吐
食べ過ぎて消化機能が限界に達すると、体が自然に食べ物を排出しようとして「吐き気」や「嘔吐」を伴うことがあります。これは体の防御反応でもありますが、脱水症状や体力の消耗につながります。
腹痛
食べ過ぎは腸にまで負担を与え、腸の動きの乱れを引き起こすことで「腹痛」につながります。特に消化しにくい食べ物や冷たい飲み物を一緒に摂取すると起こりやすいです。
食べ過ぎによる体調不良を防ぐには?

食べ過ぎは胃もたれや胸やけといった一時的な不調を招くだけでなく、長期的には生活習慣病のリスクを高める大きな要因となります。特に肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症などは、食べ過ぎと密接に関係しており、日常的にカロリー過多な食生活を続けることで、将来的に心筋梗塞や脳卒中といった重篤な疾患を引き起こす可能性もあります。
健康を維持するためには、食べ過ぎを防ぎ、消化器系への負担を減らすことが不可欠です。まず、規則正しい食生活を心がけるのが基本です。食事の時間を一定にし、よく噛んでゆっくり食べることで満腹中枢が働きやすくなり、必要以上に食べ過ぎるのを防ぐことができます。満腹になるまで食べるのではなく、「腹八分目」を意識することも重要なことです。
また、脂っこい料理や甘いものの過剰摂取は控え、野菜や発酵食品、食物繊維を含む食品を多く取り入れるのも大切で、それにより食べ過ぎによる不調を予防できます。
食べ過ぎてしまった際の対処法

いくら意識していても食べ過ぎてしまうことはあるものです。食べ過ぎてしまった際には、まず無理に消化を進めようとせず、胃腸を休ませることが大切です。食後すぐに横になると胃の働きが妨げられ、胃もたれや胸やけの原因になってしまうこともありますので、背筋を伸ばして安静に過ごすのが望ましいでしょう。
白湯や常温の水を少しずつ飲むのも効果的ですが、冷たい飲み物や炭酸飲料は胃腸に負担をかけるため控えるのが無難です。消化を促すために軽く散歩するのも効果的ですが、激しい運動は逆効果となるため避けましょう。
胃薬など市販薬を正しく活用するのも一つの方法です。また、翌日の食事で油ものや高カロリーの食事を控え、消化の良いおかゆやスープ、野菜中心の献立にすることで胃腸を休ませることができます。加えて、アルコールやカフェインも胃に負担を与えるため、食べ過ぎてしまった直後や翌日は控えたほうが良いです。
食べ過ぎには要注意
食べ過ぎは一時的な胃もたれや胸やけ、吐き気といった不快感を引き起こすだけでなく、長期的には生活習慣病のリスクを高める要因となります。特に現代は外食や高カロリー食品が身近にあり、知らず知らずのうちに食べ過ぎてしまうことも少なくありません。
大切なのは、腹八分目を意識し、日頃からよく噛んでゆっくり食べる、バランスの取れた食事を心がけることです。万一食べ過ぎてしまった際は、胃腸を休めることを意識し、体を整えましょう。