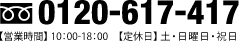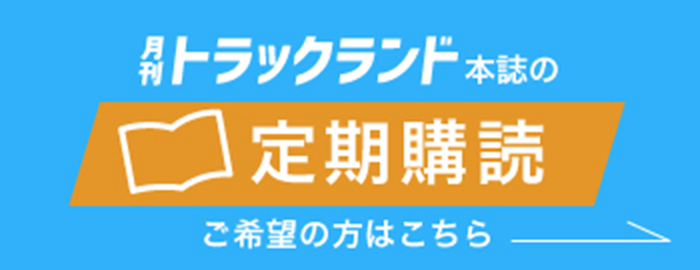近年、環境問題への関心の高まりとともに、トラックに求められる基準やルールも大きく変化しています。特にディーゼル車は、物流や産業を支える重要な存在でありながら、大気環境への影響が懸念されています。
そうした背景から導入されたのが、ディーゼル車を対象とする排ガス規制です。今回の記事では、その規制の位置づけや社会的な意味、そして物流・運送業界やトラック利用者に求められる対応について解説していきます。
ディーゼル車の排ガス規制とは?
大気汚染の原因となる窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)などの排出を抑制するために設けられた規制のことです。
特に都市部では健康被害や環境負荷が問題視され、規制強化が進められてきました。規制の内容は国や自治体ごとに異なりますが、一定の基準を満たさない車両は運行を制限されたり、改造・対策を求められるケースがあります。
歴史
日本におけるディーゼル車排ガス規制は1970年代の自動車排出ガス規制に端を発します。当時は光化学スモッグや大気汚染が社会問題化し、ガソリン車・ディーゼル車ともに排ガス削減が急務となりました。
1990年代以降は特にディーゼル車の排出ガスが注目され、2000年代にかけて東京都や神奈川県など大都市圏で「ディーゼル車規制条例」が制定されます。
それにより、対象地域では古い規制未対応車は都心部に乗り入れできなくなり、DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)や低公害ディーゼル車の普及が進みました。
対象地域
排ガス規制の対象地域は、主に大気汚染の影響が大きい都市部です。代表的なのが「首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)」と「中京圏(愛知県、三重県)」で、それらの地域では条例に基づいて規制が実施されています。
また、大阪府・兵庫県など一部の関西圏でも同様の取り組みが進められていますが、大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改正され、2022年3月末をもって流入車規制は廃止されました。ただし、自動車NOx・PM法に基づく対策は引き続き実施されています。
対象車
対象となるのは燃料の種類が「軽油」と記載されているディーゼル車です。自動車検査証(車検証)の燃料欄で確認することができます。
対象となる主な車種は以下の通りです。
①貨物自動車(1・4・6ナンバー)
②乗合自動車(乗車定員11人以上:2ナンバー、一部5・7ナンバー)
③特種用途自動車(8ナンバー)
一方で、一般的な乗用車(3・5・7ナンバー)は規制の対象外です。
また、規制対象となる型式は以下に分類されます。
①記号のない昭和54年頃までに製造された車両
②U、W、S、P、N、K、KA、KB、KC
③KE、KF、KG、KJ、KK、KL、HA、HB、HC、HE、HF、HM
※③に該当する一部の車両は基準に適合しているケースもあります。
参考:ディーゼル車規制の内容
ディーゼル車の排ガス規制の罰則について

基準を満たさない車両を規制地域で使用し続けると、行政から運行禁止命令が出されます。さらに、その命令に違反して運行した場合には、氏名公表や、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、各都県では取り締まりを行っている自動車公害監察員(いわゆる自動車Gメン)が配置されており、車両の使用状況を監視・指導しています。違反が発覚した場合には厳正な対応が取られます。規制を軽視すると事業活動にも大きな影響を及ぼすため、車両の更新や対策を怠らないことが重要です。
排ガス規制の主な対策

ディーゼル車の排ガス規制に対応するための主な対策を紹介します。
規制対応装置の取り付け(DPF・酸化触媒)
排ガス規制に対応するための代表的な方法が、DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)や酸化触媒装置の取り付けです。DPFは排気ガス中に含まれる粒子状物質(PM)をフィルターで捕集し、定期的に燃焼させて除去する仕組みです。
一方、酸化触媒は排気ガス中の一酸化炭素(CO)や炭化水素(HC)を酸化反応によって無害な二酸化炭素や水に変換し、環境への影響を低減します。それらの装置は基本的に後付けも可能で、古い車両でも規制をクリアできるように改造できます。ただし、取り付けにはそれなりの費用がかかり、定期的な点検・清掃が必要であり、メンテナンスを怠ると性能が低下するリスクがあるため、運用には注意が求められます。
関連記事:トラックのDPFとは何?仕組みやメンテナンス方法を解説
低公害ディーゼル車・新型車への乗り換え
根本的な排ガス対策として有効なのが、低公害ディーゼル車や最新の新型車への乗り換えです。最新のディーゼル車には、DPFやSCR(選択触媒還元装置)といった排ガス浄化技術が標準装備されており、NOxやPMの排出量を削減できます。
古い規制未対応車を長期間使用するよりも、車両更新によって将来的な規制違反のリスクを回避できるほか、燃費性能や走行安定性の向上による経済的なメリットも期待できます。さらに、補助金や助成制度を活用することで導入コストを軽減できる場合もあるため、長期的な事業継続を考えるうえで現実的かつ効果的な対策といえます。
運行ルートや運用方法の見直し
規制地域を通過するだけでも違反となるため、運行ルートや運用方法の見直しも重要な対策です。事前に物流ルートを検討し、規制対象エリアを避けた経路を設定することで、基準未対応車であっても違反を回避することが可能です。
また、配送拠点を規制区域外に設けたり、積載効率を高めて運行回数を減らすなど、運用方法を工夫することで環境負荷の軽減とコスト削減を両立できます。装置や車両に頼るのではなく、運用面での工夫を重ねるという方法もあります。
ディーゼル車の排ガス規制について
ディーゼル車の排ガス規制は、大気環境を改善し、健康被害や地球温暖化を抑制するために設けられた重要な仕組みです。対象地域や車両の基準は年々厳格化しており、事業者にとっては法令順守と持続可能な事業運営の両立が求められ、DPFといった装置の導入、新型車への買い替え、ルートの見直しなどの対策が取られています。
なお、トラックの整備や買い替え、中古車導入をご検討中の方は、ぜひトラックランドにご相談ください。全国対応で中古トラック・商用車の販売、買取、リース(サブスク)など幅広いサービスを提供しています。
グループ会社の陸送ネットでは登録・車検・整備・陸送までをワンストップで対応。日常のメンテナンスから車両の入れ替えまで安心してお任せいただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
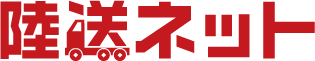
車両の陸送・登録・車検・整備を手掛け、全国対応でスムーズな車両移動をサポート。特殊車両や大型車両にも対応し、法人・個人を問わず幅広いニーズに応えています。
この記事を監修した人
 トラックランド管理人:高良
トラックランド管理人:高良
神奈川県出身。株式会社タカネットサービスの9年目の社員。
これまでに監修した記事は200件以上!中古トラックに関する豊富な知識と経験を活かし、中古トラック業界の最新情報やお役立ち情報を発信しています。
実際のトラック販売やメンテナンスにも精通しており、読者にとって有益な情報をわかりやすく提供することを心がけています。
趣味は野球観戦で、休日には球場でリフレッシュするのが楽しみの一つ。
「月刊トラックランドオンライン」にて、中古トラック選びのコツや業界の最新情報を発信中。
ぜひチェックしてください!