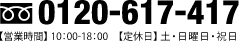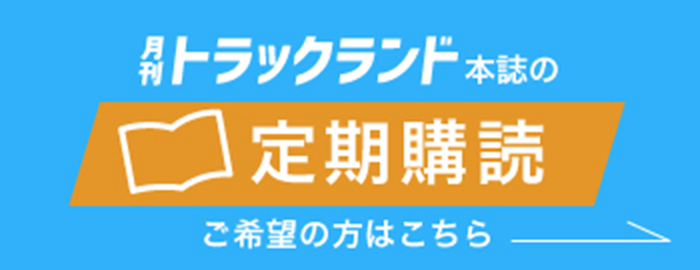私たちの生活や経済活動を支える「物流」の中心を担うのが貨物自動車です。建材や食品、日用品など、あらゆる物資を運搬するのに使われており、街中から高速道路まで、日々多くの貨物車が走行しています。
しかし一口に「貨物自動車」といっても、実はその種類や区分は多岐にわたります。この記事では、「貨物自動車とは何か」をテーマに基本的な知識から、種類や特徴、法制度・免許などについて解説します。
貨物自動車とは?
貨物自動車とは、「貨物を運搬するために使用される自動車」を指します。車両の後部に荷物を積載するための荷台や荷室を備えており、使用目的に応じて様々な装備(架装)が施されます。
積載量や走行性能、安全性を重視して設計されており、個人の移動ではなく、モノの流通・運搬を支える車両として、物流業、建設業、農業など多くの産業で用いられています。
普通自動車との違い
普通自動車と貨物自動車の違いは「目的」にあります。普通自動車は人の移動を主な目的とした車両で、乗用車やミニバン、SUVなどが含まれます。一方、貨物自動車は荷物の運搬を主な用途として設計されており、構造や法的な分類、使用要件が異なります。
構造面では、普通自動車が快適性や乗員スペースを重視しているのに対し、貨物自動車は荷台スペースや積載性を優先して設計されている点が特徴です。
貨物自動車の種類

貨物自動車の種類を「車両総重量による分類」「構造・荷台による分類」「用途による分類」に分けて解説します。
車両総重量による分類
車両総重量(車体+乗員+最大積載量の合計)によって、大型・中型・準中型・小型に分類されます。
大型車
車両総重量が11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の車両。主に長距離輸送や大量の荷物を運ぶ用途で使用されます。
中型車
車両総重量7.5トン以上11トン未満、または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の車両。
準中型車
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、または最大積載量2トン以上4.5トン未満の車両。
小型車
小型自動車の規格で作られたトラックで主に地域配送や小口輸送などに使われます。
構造・荷台による分類
車体構造や荷台の形状・機能によっても分類されます。
バン
荷台が密閉された箱型構造になっており、雨風や外気から積荷を守ることができます。食品、衣類、精密機器など、水濡れや外部環境に敏感な荷物の輸送に広く使用されています。荷室はアルミ製で軽量なものが多く、耐久性と積載効率のバランスに優れています。防犯性も高いため、高価な商品や盗難リスクのある荷物にも適しています。
ウィング
荷台の側面が羽のように大きく開閉する構造の車両で、効率的な積み下ろしを可能にします。フォークリフトによるパレット荷役がしやすく、物流センター間の幹線輸送や定期便で活躍しています。荷物の積み込み・積み下ろしが短時間で行えるため、作業効率や回転率を重視する業務に適しています。
冷凍冷蔵車
荷台に断熱構造と冷却機能を備え、食品や医薬品などの温度管理が必要な貨物を輸送するための車両で、品質保持が求められる商品に対応できます。生鮮食品や冷凍食品の配送をはじめ、製薬や材料の輸送にも使用されます。車両によっては複数温度帯に対応できる2室式や、急速冷却装置付きのモデルもあり、配送ニーズに応じた選択が可能です。
用途による分類
使用用途による分類もあります。
事業用貨物自動車
運送業者などが荷主から依頼を受け、有償で貨物を運搬するために使用される車両で、「緑ナンバー」で登録されるのが特徴です。その中には「運行」「一般」「特定」といった区分が存在し、「運行」は定期的に決まったルートでの中・長距離輸送に用いられ、「特定」は特定の荷主の専属車両、「一般」は柔軟に多様な荷主に対応する集配用車両を指します。
自家用貨物自動車
自社の製品や資材の運搬など、自社業務にのみ使用される車両は「自家用貨物車」として「白ナンバー」で登録され、有償輸送はできません。
軽貨物自動車
軽トラックや軽バンなどの軽貨物車両については、個人事業主が使用する「黒ナンバー」の営業用と、農業や店舗配送などに用いられる自家用の軽貨物車に分かれます。
貨物自動車に関する法制度・免許

貨物自動車は物流の根幹を支える存在であり、安全性や効率性を確保するために、法律や運転免許制度が整備されています。
ここでは、貨物自動車に関する主な法制度と、運転に必要な免許について解説します。
法制度
道路交通法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法などの法令に基づき、運行や整備、事業の許認可に関するルールが定められています。
例えば、他人の貨物を有償で運ぶには「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要で、国土交通省による審査や営業所・車庫の要件なども設けられています。また、運行管理者の配置、安全運行管理、定期点検の実施も義務化されており、違反すれば行政処分や業務停止につながる場合もあります。
さらに、積載物が危険物や高圧ガスである場合は、消防法や高圧ガス保安法などの特別法が適用され、車両表示や取り扱い資格の取得も必要です。
免許
貨物自動車の運転には、車両総重量や最大積載量に応じた運転免許が必要です。普通免許で運転できるのは最大積載量2トン未満・車両総重量3.5トン未満の車両で、それ以上は「準中型」「中型」「大型」といった区分の免許が求められます。
準中型免許
最大積載量2トン以上4.5トン未満、総重量3.5トン以上7.5トン未満の貨物車を運転でき、18歳以上であれば運転経験がなくても取得可能。
中型免許
最大積載量4.5トン以上6.5トン未満、総重量7.5トン以上11トン未満の車両が対象で、20歳以上、かつ普通免許(または準中型)を取得して2年以上の運転経験が必要。
大型免許
最大積載量6.5トン以上または総重量11トン以上が対象で、21歳以上で普通免許(または中型)を取得して3年以上の運転経験が必要。
貨物自動車について
貨物自動車は、荷物を運搬することを主な目的とした自動車であり、普通自動車とは構造や用途、登録区分などに明確な違いがあります。サイズや構造、用途によって種類が存在し、法制度や免許制度によって管理されています。
物流をはじめとした様々な産業を支える重要な存在であり、使用目的や積載量に応じた適切な車両の選択と、法令遵守が求められます。
なお、貨物自動車の購入や買い替えをご検討中の場合には、ぜひ「トラックランド」をご利用ください。トラックランドでは、中古の貨物自動車や商用車の販売・買取・リース(サブスク)など、幅広いサービスを展開しています。
ご希望の仕様や条件に合った車両が在庫にない場合でも、全国のネットワークを活かし、最適な1台を迅速にお探しすることが可能です。用途やご予算に応じた柔軟な対応も可能ですので、ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
この記事を監修した人
 トラックランド管理人:高良
トラックランド管理人:高良
神奈川県出身。株式会社タカネットサービスの9年目の社員。
これまでに監修した記事は200件以上!中古トラックに関する豊富な知識と経験を活かし、中古トラック業界の最新情報やお役立ち情報を発信しています。
実際のトラック販売やメンテナンスにも精通しており、読者にとって有益な情報をわかりやすく提供することを心がけています。
趣味は野球観戦で、休日には球場でリフレッシュするのが楽しみの一つ。
「月刊トラックランドオンライン」にて、中古トラック選びのコツや業界の最新情報を発信中。
ぜひチェックしてください!