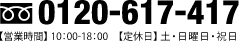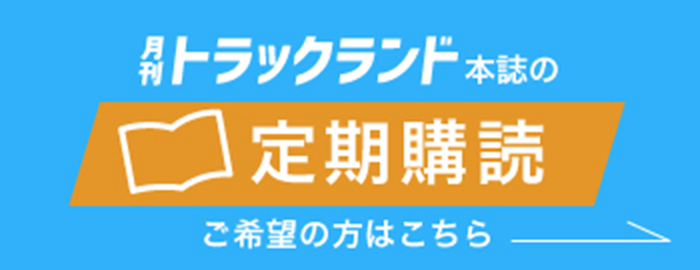年末年始には様々なイベントがあり、家族や友人との集まりが増える一方で、暴飲暴食や生活リズムの乱れ、運動不足などが原因で「正月疲れ」を感じる人が少なくありません。
今回は、正月疲れの主な症状や原因を紹介し、体調を整えるための正しい対策や解消法を解説します。
正月疲れとは?
年末年始の休暇中に生じる生活リズムの乱れや飲食習慣の変化によって、体調不良や疲労感を感じる状態のことを指します。
楽しいイベントが多い一方で、暴飲暴食や睡眠不足、運動不足が重なることで、休み明けに仕事や日常生活への切り替えがうまくいかず、体のだるさやストレスを感じる方は多いです。長期休暇後の仕事や日常生活に戻るのがつらいと感じる場合、正月疲れの影響が考えられます。
主な症状・原因

正月疲れによって現れる症状は人それぞれですが、特に以下のような体調不良を感じることが多いです。
・全身のだるさ・倦怠感
・胃腸の不調
・むくみ・体重増加
・頭痛や肩こり
・集中力の低下
・やる気が出ない
その主な原因は、以下のような生活習慣の変化によるものが多いです。
暴飲暴食による消化器への負担
おせち料理やお餅、お酒など、普段とは異なる食生活が続くことで、胃腸に負担がかかり、消化不良や胃もたれを引き起こすことがあります。また、高カロリーな食事が増えることで、体重の増加やむくみの原因にもなります。
睡眠リズムの乱れ
年末年始は夜更かししがちになり、就寝・起床時間が不規則になることで体内時計が乱れ、疲労感が抜けにくくなることがあります。また、食事や飲酒の時間が変わることも、睡眠の質に影響を与えます。
運動不足による血流の悪化
冬は寒さの影響で外出する機会が減り、運動不足になりやすい時期です。特に、長時間のテレビ視聴やスマホ操作が増えることで、筋肉のこわばりや血流の悪化が起こり、肩こりや頭痛、冷えを感じやすくなります。
ストレスや疲れの蓄積
年末の大掃除や帰省、親戚付き合いなど、意外と心身に負担がかかるイベントが多いのも正月疲れの原因です。普段とは異なる環境で過ごすことで、気を遣う場面が増え、休暇中でも知らず知らずのうちにストレスが溜まることがあります。
長期休暇による生活リズムの変化
年末年始は仕事が休みになるため、「何もしない」時間が長くなり、活動量が減少します。その結果、脳が休息モードから抜け出しにくくなり、仕事モードへの切り替えが難しくなることがあります。
正月・連休疲れ対策・解消法

長い休暇の後に感じる「正月疲れ」「連休疲れ」は、生活リズムの乱れや食生活の変化、運動不足が主な原因です。疲れを解消するために以下のことを意識することが大切です。
胃腸を整える
休み明けは、おかゆや味噌汁、野菜スープなどの消化に優しい食事を意識し、胃を休めることが大切です。脂っこいものや甘いものは控えめにし、食物繊維を多く含む野菜や果物を摂ることで腸内環境を整えましょう。また、水分補給を忘れず、白湯やハーブティーで体を内側から温めると代謝が促進されます。アルコールやカフェインは胃腸に負担をかけるため、休み明けはできるだけ控えるのが理想的です。
睡眠の質を高める
十分な睡眠をとることで、心身の疲れを効率よくリセットし、休み明けの体調不良を防ぐことができます。寝る前のスマホやカフェイン摂取を控え、照明を暖色系にするなど、リラックスできる環境を整えることが重要です。また、就寝前に軽いストレッチや深呼吸を取り入れることで、副交感神経が優位になり、より深く質の良い睡眠ができます。しっかりとした睡眠を確保することで、疲労回復だけでなく、集中力や免疫力の向上にもつながります。
軽い運動をする
休み明けは軽い運動を取り入れ、血流を良くすることも大切です。朝のストレッチで首や肩をほぐし、深呼吸をしながら体を動かすことで、自律神経が整います。また、1日15~30分のウォーキングは代謝を高め、疲労回復にも効果的です。定期的な軽い運動は、心身のリフレッシュやストレス軽減にも寄与し、仕事や日常生活のパフォーマンス向上にもつながります。
正月・連休疲れを解消するためには
正月疲れは、生活リズムの乱れ、暴飲暴食、運動不足などが原因で、体調不良や倦怠感を引き起こします。正月・連休疲れを解消するためには、生活リズムを整え、胃腸をいたわり、適度な運動を取り入れることが大切です。
規則正しい生活やバランスの良い食事を意識し、軽いストレッチやウォーキングで血流を促すことで、体の不調を改善できます。しかし、無理をするのは禁物ですので、焦らずに徐々に生活リズムを戻していきましょう。