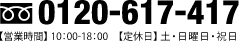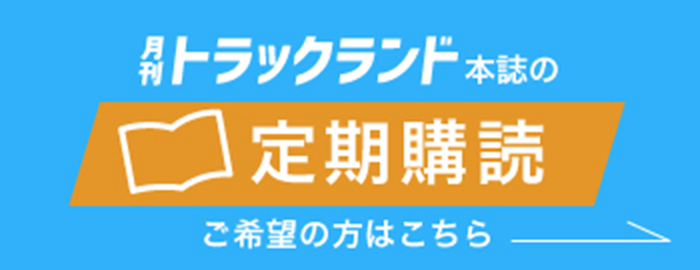大型トラックやバスなどの重量車両には、安全性を確保するために「エアブレーキ」と呼ばれる制動システムが採用されています。一般的な乗用車・小型トラックとは異なる仕組みで、独特の操作感や特徴があるため、難しいと感じる方も多く、仕組みや使い方を正しく理解しておくことが重要です。
今回の記事では、エアブレーキの概要から仕組み、使い方のコツ、注意点などを解説します。
エアブレーキとは?
圧縮空気の力を利用して車両を制動させるブレーキシステムのことです。主に大型トラックやバスなどの大型車両に採用されており、高い制動力があります。
乗用車や小型トラックに多い油圧式ブレーキとは異なり、空気圧によって作動し、大型車両のような重い車体でも安定的に制御できるのが特徴です。
エアブレーキには、すべての制動を空気圧で行う「フルエアブレーキ」や、油圧式と組み合わせた「空気油圧複合式ブレーキ(エアオーバーハイドロリックブレーキ)」などがあります。
構造・仕組み
エアブレーキは、コンプレッサー(空気圧縮機)、エアタンク(圧縮空気の貯蔵装置)、ブレーキバルブ、ブレーキチャンバー、ブレーキシューなどで構成されています。まず、エンジンの動力を使ってコンプレッサーが空気を圧縮し、それをエアタンクに蓄えます。
ドライバーがブレーキペダルを踏むと、ブレーキバルブを通じて圧縮空気がブレーキチャンバーに送られ、内部のダイヤフラム(膜)を押し出します。その力が機械的にブレーキライニングへと伝わり、ドラムやディスクを押さえて車輪の回転を抑制します。
エアブレーキの使い方・コツ

エアブレーキは、特有の操作感のため慣れていないと難しく感じることでしょう。正しい使い方を理解することで、スムーズな運転と安全確保につながります。
以下で主なポイントを紹介します。
早めの操作を心がける
エアブレーキは構造上、ペダルを踏んでから制動がかかるまでにわずかなタイムラグがあります。そのため、乗用車や小型トラックの感覚でブレーキ操作をすると止まりきれず、ヒヤッとする場面が生じかねません。特に荷物を積んでいると車体の慣性力が強くなるため、早めの操作が基本です。車間距離を広めにとり、信号や交差点では余裕をもった減速を心がけることで、安心・安全な運転につながります。
かかとを支点に足裏全体で踏む
エアブレーキは、踏み方を意識することも重要です。ブレーキペダルを踏む際は、かかとを支点にして足裏全体でじわっと踏み込むのが理想的。つま先だけで急に力を入れると、急制動になりやすいです。荷物を積んだ状態では、安定した姿勢での操作が制動距離にも影響を与えるため、足元の使い方には十分注意しましょう。
エンジンブレーキと併用する
長い下り坂や減速時間が長くなる場面では、エアブレーキに頼りすぎると熱を持ちすぎて「フェード現象」が起きやすくなります。そうした場面では、エンジンブレーキなどの補助制動装置を併用するのが基本です。エア圧の消費を抑えるだけでなく、ブレーキ系統の負担も軽減できるため、ブレーキの寿命延長にも効果的です。
エアブレーキの使用に関する注意点

エアブレーキは、使い方を誤ると制動力の低下や重大なトラブルにつながるおそれがあります。
以下のポイントに注意することが重要です。
バタ踏みをしない
エアブレーキにおいて、ブレーキペダルを連続して細かく踏む「バタ踏み」は厳禁です。その操作を繰り返すとエアタンクの圧力が急激に低下し、制動力が不足する原因になります。特に渋滞中などで不用意にブレーキを多用すると、ブレーキが効かなくなる恐れがあり危険です。踏むときは一度でしっかり、離すときは無駄なく、というリズムを意識しましょう。
エア圧ゲージを常に確認する
エアブレーキは圧縮空気によって作動するため、エア圧が不足している状態では正しくブレーキが効かなくなります。そのため、日常点検や走行中にはエア圧ゲージをこまめに確認することが重要です。通常は7〜10kg/cm²が適正範囲とされており、それを下回る場合は走行を中止する必要があります。警告音やランプが点灯している場合は、見逃さずに確実に対処しましょう。
エアブレーキが効かない場合に考えられる原因
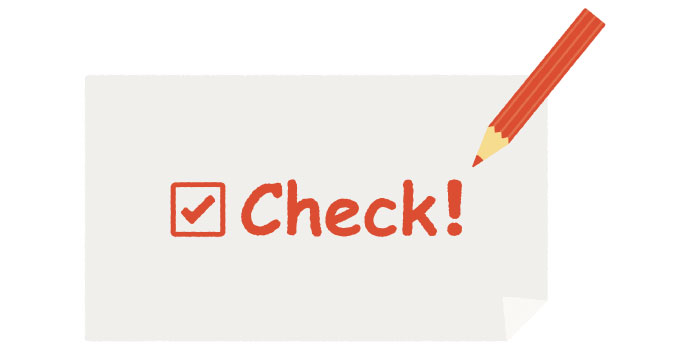
エアブレーキが効かない、または効きが悪いと感じる場合に考えられる原因を解説します。
エア圧の不足・エア漏れ
もっともよく見られるのが、エアタンク内の圧力不足です。エンジン停止中にブレーキを多用したり、頻繁なバタ踏みを行ったりすると、圧力が一時的に不足し、十分な制動力が得られなくなることがあります。また、エア配管の継ぎ目やホースの劣化、ジョイント部分の緩みなどによるエア漏れも圧力低下の大きな要因です。わずかな漏れでも、安全性を著しく損なう可能性があるため油断は禁物です。
ブレーキチャンバー・ダイヤフラムの不具合
ブレーキチャンバーの内部にあるダイヤフラム(膜)が損傷すると、正常にブレーキ力が伝わらなくなり、制動力が大幅に低下します。ダイヤフラムの破れや変形は目視で確認しづらいため、ブレーキの効きが悪いと感じたときには、すぐに点検を依頼しましょう。長期間使用した部品は経年劣化により突然破損することもあるため、走行距離や使用年数に応じた交換計画を立てておくことも重要になります。
バルブ類の故障
エアブレーキには、圧力の流れを調整・分配するためのバルブがいくつも使用されています。それらが故障するとブレーキが作動しなかったり、逆に解除されなかったりといった異常が発生します。内部が詰まって動きが悪くなる場合もあり、見た目では判断しづらいため、定期的な点検が重要です。操作したときの反応が鈍い、踏み込み後の戻りが遅いなどの症状があれば、バルブ系統の不具合を疑いましょう。
ブレーキシューの摩耗
ブレーキシューやライニングが摩耗していると、ブレーキの踏み込みに対して思うような減速効果が得られません。特に大型トラックや重積載時には、摩耗が進行すると制動距離が著しく延び、危険な状況を招く恐れがあります。摩耗の状態は定期的な点検で確認し、必要に応じて早めに交換や調整を行うことが重要です。
トラックのエアブレーキについて
エアブレーキは大型トラック、バスなどで採用されている制動装置であり、構造や仕組みを正しく理解し、適切に使いこなすことが安全運転に直結します。日常点検やエア圧ゲージの確認、エンジンブレーキとの併用などを心がければ、トラブルの予防にもつながります。エアブレーキを正しく使い、安全かつ安定した運行を実現しましょう。
なお、エアブレーキの不具合や修理のご相談、または車両の入れ替えをご検討中の場合には、ぜひ「トラックランド」にご相談ください。全国対応で、中古トラックの買取・販売などを行っており、グループ会社の「陸送ネット」では、定期点検や修理、各種メンテナンスにも柔軟に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
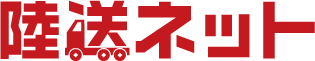
車両の陸送・登録・車検・整備を手掛け、全国対応でスムーズな車両移動をサポート。特殊車両や大型車両にも対応し、法人・個人を問わず幅広いニーズに応えています。
この記事を監修した人
 トラックランド管理人:高良
トラックランド管理人:高良
神奈川県出身。株式会社タカネットサービスの9年目の社員。
これまでに監修した記事は200件以上!中古トラックに関する豊富な知識と経験を活かし、中古トラック業界の最新情報やお役立ち情報を発信しています。
実際のトラック販売やメンテナンスにも精通しており、読者にとって有益な情報をわかりやすく提供することを心がけています。
趣味は野球観戦で、休日には球場でリフレッシュするのが楽しみの一つ。
「月刊トラックランドオンライン」にて、中古トラック選びのコツや業界の最新情報を発信中。
ぜひチェックしてください!